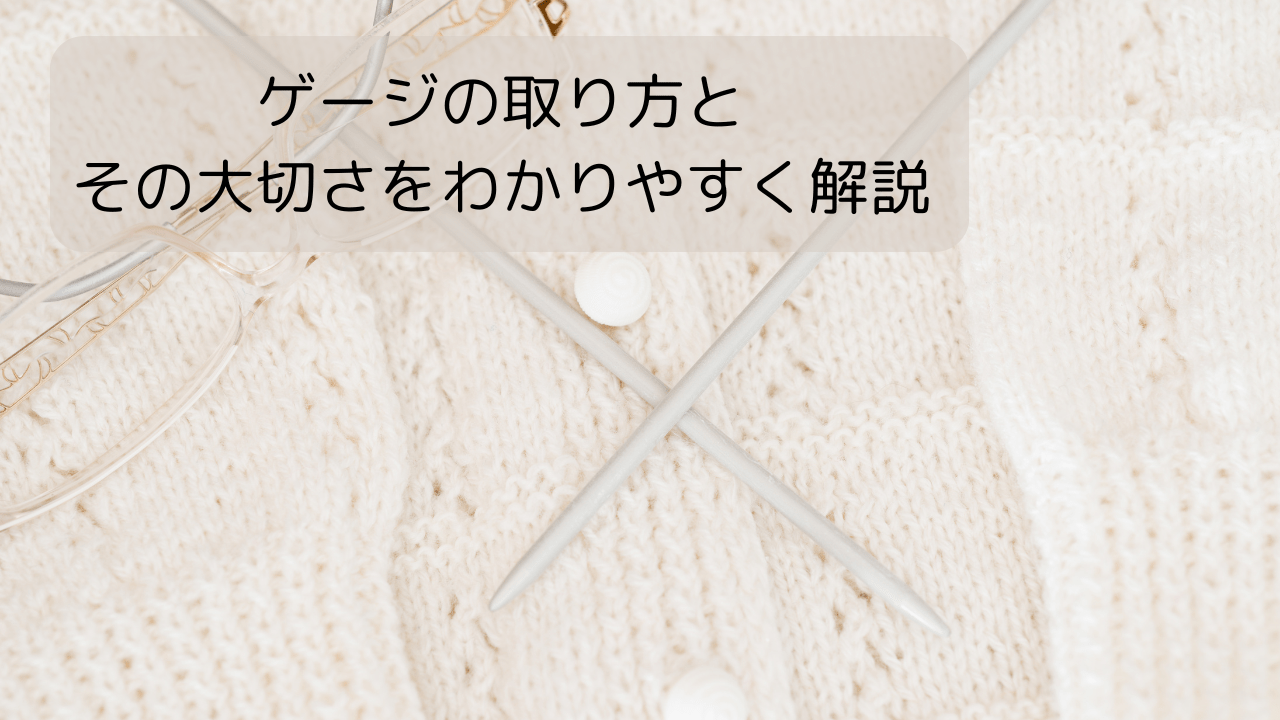編み物を始めると「ゲージ」ってよく聞きますよね。
でも、初心者さんの中には
「ゲージってなに?なんで必要なの?」
「飛ばして編んじゃダメなの?」
と思う方もいるのではないでしょうか?
ゲージってなに?
ゲージとは、
「決めた長さ(10cm)の中に、何目×何段の編み目が入るか」
を測ることです。
編み図などに
「10cm四方で20目×30段」
と書いてある場合、
10cmの中に
20目・30段の編み目ができるように
編む必要があるということ。
ゲージの役割
希望サイズの実現
編み物は、
使用する糸の種類、
編み針の号数、
編む人の手加減によって
仕上がりサイズが変わります。
ゲージを取ることで、
自分の編み方でどのような大きさになるかを
事前に確認でき、
作品が希望のサイズ通りに仕上がります。
仕上がりの品質向上
ゲージが合うことで、
作品の柔らかさや模様の美しさを
最大限に活かせます。
手加減が強すぎると硬くなり、
緩すぎると模様が崩れることがあります。
編み直しを防ぐ
ゲージを取らずに編むと、
サイズが合わずに、
解いてやり直す必要が生じることがあります。
これにより
毛糸がダメージを受ける可能性もあるため、
ゲージを取ることが大切ということがわかります。
チャットGPT:
ゲージの取り方をわかりやすく解説!
ゲージの大切さがわかったところで、
次は実際のゲージの取り方を説明します!
ゲージとるための準備
まず、必要なものを準備しましょう!
使う予定の毛糸
使う予定の針(棒針 or かぎ針)
定規 or メジャー
とじ針(編み終わりの糸処理用)
これらを準備できたら、早速編んでいきます!

ゲージの編み方(手順)
〜レシピに書いている「ゲージ」の目数より大きめに編む〜
例、レシピに「10cm四方で20目×30段」と書かれている場合、
最低でも25目×35段くらい編みます。
なぜ大きめに編むのかというと、
端の部分は伸びやすかったり形が乱れたりするので、
正確に測るために中央を測りたいためです。
〜編み終わったら〜
軽くスチームアイロンをかけます(または水通しする)。
〜定規で10cmの範囲を測る〜
あなた
チャットGPT
編み終わったら、
編み地を平らな場所に置いて、
定規やメジャーを使って、
「10cmの中に何目・何段に入っているか」を測ります。
〜ポイント!〜
測るときは、編み地を引かないように注意します。
目が見えにくいときは、目数リングなどで目印をつけると数えやすいです。
測ったゲージがレシピと違ったら?
「測ったゲージ」と「レシピのゲージ」
が違う場合は、次の方法で調整します。
目数が多すぎる(10cmの中に目が見えすぎる)
→ 針の号数を1号大きくす(例:5号 → 6号)
目数が足りない(10cmの中に目が足りない)
→ 針の号数を1号小さくする(例:5号 → 4号)
段数が合わない場合も針のサイズを調整してみましょう。
手加減で調整すると、
最後まで同じテンションを保つことが難しいため
避けたほうが良いです。
編み目は、
手加減やその日の体調、
編むスピードなどによって変化するため、
最初に取ったゲージと、途中で確認するゲージを
比較しながら進めることも大切です。
まとめ ゲージは大事!
ゲージを取ることで…
編みたい作品がレシピ通りのサイズに仕上がる。
後からサイズが合わない!と後悔せずにすむ。
編む前に、自分の編み加減のクセを知ることができる!
ゲージは、
完成品のサイズなどに直接影響するため、
特にウェアなど
サイズが重要な作品では欠かせない工程です。
初心者には面倒に感じられるかもしれませんが、
作品作りをスムーズに進めるためには、
習慣化することがおすすめです。
皆さんの編み物ライフが楽しくなりますように!